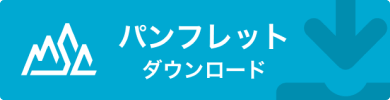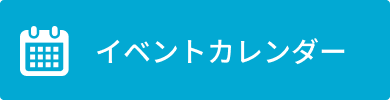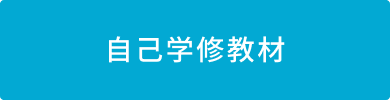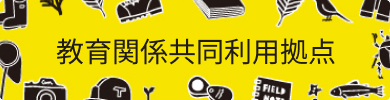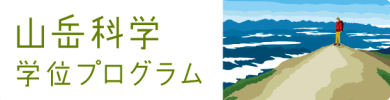2023年度研究課題一覧
随時更新しています。
| 研究課題名(受付順) | 概要 | 研究代表者・所属 | 実施期間 |
|---|---|---|---|
| 1. トビムシ目の比較発生学的研究 | 六脚類の進化において重要な分類群であり、しばしば狭義の昆虫類(外顎類)と姉妹群とされる内顎類3目(トビムシ目、カマアシムシ目、コムシ目)の形態形成の過程から六脚類の形態進化やその基部分岐を明らかにする。 | 富塚 茂和 十日町市立里山科学館 越後松之山「森の学校」キョロロ | 2023.4.1~2024.3.20 |
| 2. 森林におけるツル植物の純一次生産量への貢献 | 森林におけるつる植物が、森林全体の物質生産にどのような影響を与えているのかを明らかにする。 | 谷岡 庸介 筑波大学生物学学位プログラム | 2023.4.1~2024.3.31 |
| 3. 植生履歴の異なる草原性植物群集間の花形質組成の比較 | 植生履歴の異なる草原性植物群集間の花形質組成の比較を通じて、送紛に関わる機能形質(花色・花形態など)が、植物群集の集合規則に与える影響を評価する。 | 石井 博 富山大学大学院理工学研究部 | 2023.5.17~2023.10.30 |
| 4. 山地の森林フェノロジーと夜間冷気流出の関係 | 菅平から上田での気象観測、および菅平高原実験所での落葉樹の開葉・落葉の観測を行い、冷気流とフェノロジーとの関係を明らかにする。 | 加古 祐貴 筑波大学地球科学学位プログラム | 2023.4.1~2024.3.31 |
| 5. 菅平盆地で形成される接地逆転層「冷気湖」における気温変動の解明 | 盆地底と菅平高原実験所との気温差から求めた大気安定度指標を用いて、気温の長周期変動の特徴を明らかにする。また、大気安定度は、夜間冷却の強さと大気中の物質輸送過程に関係することから、気温の長周期変動の特徴を用いて、盆地内の夜間冷却と夜間の気温形成のメカニズムと安定層内における熱やエネルギー、そして物質輸送過程に関する知見を得る。 | 鳥谷 均 NPO法人圃場診断システム推進機構 | 2023.4.1~2024.3.31 |
| 6. ブナ葉枯れ病線虫の調査 | ブナの葉の特徴的な病巣からブナ葉枯れ線虫が分離されるものの、病原体としての断定に至っていない。今回、病徴を示すブナから線虫を採集して季節変遷を追い、病気との関連を調べていく。 | 長谷川 浩一 中部大学応用生物学部環境生物科学科 | 2023.4.4~2024.3.31 |
| 7. カエデ属における冬季の日長認識に関与する光受容器官の適応進化 | 落葉樹には、冬から春にかけての日長の変化を認識し、開芽時期を調節する種がいる。これまでの調査から、カエデ属ではこの日長認識に機能する光受容器官に種間変異があり、これはは生育している光環境と関連することが明らかとなった。本調査では、光受容器官の種間変異が光環境に対する適応進化によって形成されたのか否かを明らかにするため、カエデ属各種が生育している光環境を定量化することを目的とする。 | 大野 美涼 岩手大学大学院連合農学研究科(弘前大学配属) | 2022.10.17~2024.3.31 |
| 8. 日本産カエデ属樹種における性表現と繁殖投資との関係 | 雌雄異株植物は、「花粉制限が起きやすい」「雄株が種子散布に貢献しない」という不利を抱えている。不利を補うための要因として「花数や種子数が多い」「種子サイズが大きい」という仮説がある。本研究では先述の仮説を確かめるために、カエデ属の雌雄異株樹種と両性樹種の間で、花数、種子数、種子サイズを比較し、性表現と繁殖特性の関係を調べる。 | 加藤 拓磨 大阪公立大学大学院理学研究科生物学専攻 | 2023.4.20~2023.12.31 |
| 9. 交通騒音が鳥類による緑地利用に及ぼす影響の検証 | 交通網の拡大に伴い交通騒音が問題となっており、鳥類の個体数や繁殖成績などに悪影響を及ぼすことが報告されている。近年野外に騒音を導入する実験手法が確立したことで、他の条件を揃えた上で騒音による影響を調べることが可能になった。また、樹木と草原とでは、音の減衰パターンが異なることが知られている。したがって、騒音による鳥類への影響は植生間で違いが見られると考えられる。本研究では鳥類の生息地内に交通騒音を導入することで、騒音による影響を鳥類の生息環境ごとに評価することを目的としている。本研究で得られる知見は生物多様性の保全に貢献できることが期待される。 | 鈴木 龍晟 筑波大学生物学学位プログラム | 2023.5.8~2024.3.31 |
| 10. ➀植生再生過程における植物-送粉者ネットワークの構造および植物の繁殖成功の変化 ➁花を利用する捕食者と虫媒植物の関係 | ➀本研究では、造成時期が異なる新・古スキー場の送粉ネットワーク(PN)の状態や優占植物種の繁殖成功を比較し、以下の予測を検証する。新スキー場は、古スキー場に比べ、(1)PNはジェネラリスト化し、虫媒種の結実率が低くなる。また、新スキー場では、(2)造成時期が古い場所ほど、虫媒植物の種・機能的多様性が高くなり、PNはよりスペシャリスト化している。 ➁菅平高原実験所内での長期間にわたるクモ類及び開花植物の調査を行うことで、 1)クモ類は狩場として多様な種に訪花されるジェネラリスト媒の開花植物を多く利用する 2)クモの分類群によって狩場とする植物の形質及び利用場所が異なる 以上二つの仮説を検証することを目的とする。 | 平山 楽 神戸大学人間発達環境学研究科 | 2023.4.1~2024.3.31 |
| 11. 一般市民との協働による生涯学習の場「みんなの標本庫」での菌類及び地衣類標本整備に向けた手法開発 | 菅平高原実験所の標本庫を市民との協働で再整備し、地域に根差し且つ社会的意義のある場としての利活用を深化させる。 (2023年度笹川科学研究助成) | 山中 史江 筑波大学生命環境系技術室(菅平高原実験所) | 2023.4.1~2024.3.31 |
| 12. 降積雪を中心とした気象測器の設置環境と測定値の関係に関するデータ収集と調査 | 既存の気象観測に含まれる測定値に対する観測点周辺環境の影響を評価するための基礎資料の収集 | 西森 基貴 農研機構・農業環境研究部門 | 2023.4.1~2024.3.31 |
| 13. 日本およびユーラシア大陸のツキノワグマの保全遺伝学的研究 | 日本およびユーラシア大陸のツキノワグマの保全遺伝学的研究のためのデータ解析補助・サポートを津田吉晃准教授にしていただく。 | Guskov Valentin(グシコフ・ヴァレンティン) Federal Scientific Center of the East Asia Terrestrial Biodiversity(ロシア)、森林総合研究所東北支所(国内滞在期間) | 2023.5.8~2023.6.30 |
| 14. 生物多様性影響評価に必要な自生セイヨウナタネ(Brassica napus)の生態遺伝学的研究 | 日本は現在多くの遺伝子組換えナタネを輸入している。輸入に際してカルタヘナ法を基に生物多様性影響評価が実施される。わが国には、明治次代後期より日本全国的に河川敷の主要構成種である自生ナタネが存在しているが、外来種であるという観点から生物多様性影響評価から除外されている。本研究では、外来種であるからといって自生ナタネをカルタヘナ法から除外するのではなく、遺伝子組換えナタネの導入による環境影響評価を生態遺伝学的に研究することを目的としている。 | 柳 江莉那 筑波大学生命環境科学研究科生物圏資源科学専攻 | 2023.4.1~2024.3.31 |
| 15. 海洋生態系保全に向けた、地球温暖化で分布移動する魚類の集団ゲノミクス動態の解明 | 地球温暖化による海洋魚類への影響予測を最終目的として、カワアナゴ科魚類を対象に集団遺伝学、生物地理学、生態学、形態学および海洋物理学的研究を行い、過去~現在の遺伝構造・集団動態の歴史を解明する。 | 山川 宇宙 筑波大学大学院生命環境科学研究科生物科学専攻 | 2023.4.1~2024.3.31 |
| 16. 卒業研究:日本産担子菌門ヒラタケ型菌類の探索・分類 | 上記卒業研究に必要な技術などの習得 | 黒﨑 裕貴 筑波大学生命環境学群生物学類 | 2023.5.8~2023.5.12 |
| 17. ジェネラリスト送紛者は個体レベルでスペシャリストとなりうるか:野外環境下における検証 | 本研究では、ジェネラリスト送紛者とスペシャリスト送紛者に着目して、野外環境下において送紛者が花を連続的に訪花する際にどのような要因が影響しているのか、そして定花性的行動が植物の繁殖成功にどのように寄与するのかを明らかにすることを目的とする。 昨年度の研究において、ジェネラリストと考えられる送紛者分類群であっても、比較的同種を連続して訪花する傾向が高いことが明らかとなった。そこで今年度は、そのような連続訪花を引き起こす植物側の要因を明らかにするため、花色や植物高などに着目したプロットの設置を行う。厳密に定花性のみを評価することは難しいため、野外環境下における植物の繁殖戦略を明らかにしたい。 | 瀬尾 夏未 神戸大学人間発達環境学研究科 | 2023.6.23~2024.3.31 |
| 18. 菌類の細胞内共生細菌に関する研究 | 菅平高原実験所内より分離される菌類、特に Mortierella 属菌における細胞内共生細菌の遺伝的多様性を明らかにする。菅平高原実験所では菌類の分離に用いるリターの採集を行う。 | 高島 勇介 農研機構・遺伝資源研究センター微生物資源ユニット | 2023.5.12~2024.3.31 |
| 19. 寄生性ケカビ目菌の研究 | 菌学会に向けた実験及びデータ整理 | 前川 直人 茨城県林業技術センター | 2023.4.30~2023.5.5 |
| 20. 表層性のトビムシの採集と観察 | トビムシの採集、同定法を理解する | 長谷川 元洋 同志社大学理工学部 | 2023.6.11 |
| 21. カラマツ林の葉面積指数の連続観測による葉群フェノロジーの年次変化の評価 | 2018年12月に気候変動適応法が施行され、長野県は2019年4月に信州気候変動適応センターを設置した。信州気候変動適応センターは、気候変動の実態把握、予測、影響評価を行うことで、地域の気候変動適応策を促進することが重要な課題となっている。本研究では気候変動が信州カラマツに及ぼす影響を評価するため、カラマツ林の葉面積指数と気温の連続観測を継続し、近年の急激な気温上昇に伴う葉群フェノロジーの変化を明らかにすることを目的とする。 | 栗林 正俊 長野県環境保全研究所 | 2023.4.1~2024.3.31 |
| 22. 昆虫類の比較発生学的研究 | 昆虫群を比較発生学の観点から検討し、昆虫類の高次系統、グラウンドプランの構築を目指す。 | 町田 龍一郎 筑波大学山岳科学センター菅平高原実験所 | 2023.4.1~2024.3.31 |
| 23. 昆虫(無脊椎動物)嗜好性線虫の分類と多様性 この目的のため、今回の調査では、ハナバチ類、甲虫類の試料を手捕りで採集する。 | 昆虫(無脊椎動物)嗜好性線虫の分類と多様性、生態的関係を基礎研究として調査する。また、この過程で得られた特殊な生理、生態的特徴を持つ種類に関しては、モデル(研究材料)として、他の研究分野への応用を行う。 | 神崎 菜摘 森林総合研究所関西支所 | 2023.6.1~2023.10.31 |
| 24. 昆虫等寄生菌類に関する研究 | 水系に生育する昆虫および節足動物寄生菌の採集を行う。 | 佐藤 大樹 森林総合研究所 | 2023.6.11~2023.6.13 |
| 25. 菅平高原実験所内のアリの多様性調査 | 菅平高原実験所構内でアリ類の調査を行う。 | 近藤 正樹 近藤蟻蜘蛛研究所 | 2023.6.11~2023.6.12 |
| 26. ジェネラリスト送紛者は個体レベルでスペシャリストとなりうるか:野外環境下における検証 | 本研究では、ジェネラリスト送紛者とスペシャリスト送紛者に着目して、野外環境下において送紛者が花を連続的に訪花する際にどのような要因が影響しているのか、そして定花性的行動が植物の繁殖成功にどのように寄与するのかを明らかにすることを目的とする。 昨年度の研究において、ジェネラリストと考えられる送紛者分類群であっても、比較的同種を連続して訪花する傾向が高いことが明らかとなった。そこで今年度は、そのような連続訪花を引き起こす植物側の要因を明らかにするため、花色や植物高などに着目したプロットの設置を行う。厳密に定花性のみを評価することは難しいため、野外環境下における植物の繁殖戦略を明らかにしたい。 | 瀬尾 夏未 神戸大学人間発達環境学研究科 | 2023.6.23~2024.3.31 |
| 27. 低地と高原地帯の植生の変化 | 本校の探究学習の一環として低地と高原地帯の植生の違いと変化、また菅平高原の気候について見て、聞いて、匂いで、肌で感じることを目的に自然学習を行う。とともに菅平高原の抱える膨大な自然資源をどのようにして観光誘致に結びつけているのか社会学的・観光学的観点から考察する。 | 関口 和也(小林 稜弥) 上田西高等学校 | 2023.5.31 |
| 28. 半自然草原下におけるイノシシの掘り起こし深度の違いが草地植生及び送粉者に与える影響 | 攪乱は生態系の構造や動態に変化をもたらす主要因の一つである。生態系の中でも、草原は攪乱とのかかわりが強い。草原には特有の動植物が見られ、生物多様性が高いことが知られている。しかし、管理者不足などの社会的な問題に起因する攪乱機会の減少によって、草原生態系は貴重な存在になりつつある。攪乱の中でも、草食動物による攪乱は、自然由来の攪乱として、植生などに影響を与えている。例えば、シカなどによる地上部の植物の摂食やイノシシによる土壌の掘り起こしがあげられる。その中でも、イノシシによる土壌の掘り起こしは、地上部のみならず地下部に対しても直接的な影響をもたらすものから、ほかの大型採食動物には見られない特異的な攪乱であると言える。くわえて、掘り起こしの深さにはばらつきがみられる。これは、同一行動内で攪乱強度に多様性が存在することを意味する。既往の研究で、イノシシの掘り起こしが植物群落の多様性に関与する可能性が言及されているが、掘り起こし強度(深度)の違いが植物群落にもたらす効果について言及した事例、特に草原生態系に対する知見は存在しない。さらに掘り起こしがもたらす草原生態系への間接的な影響についても、これまで評価されていない。ここで言う間接的な影響として、植物群落を介した送粉者への影響が考えられる。一般的に、植物の多様性と送粉者の多様性には相関があることから、イノシシによる掘り起こし深度にともなう植物群落の多様性が送粉者の多様性に作用している可能性は否定できない。しかし、掘り起こしがもたらす植物ー送粉者共生系への作用の理解はいまだ進んでいない。 そこで本研究では、イノシシによる掘り起こしの生態学的意義の解明に向け、草原における本種の掘り起こし、植生物、送粉者の三者関係を明らかにする。その際、特に掘り起こしの深さがもたらす効果に着目して調査を実施する。 | 梅田 悠起 近畿大学大学院農学研究科環境管理学専攻 | 2023.6.20~2024.3.31 |
| 29. 実習科目名「自然環境調査法」:ススキ草原と夏緑広葉樹林に生息する生物を対象とした,生物調査法に関する実習 | 生物の採集法、観察法、標本作製法、同定法を実地で学ぶことが目的である。菅平高原実験所内の草原植物、草原性および森林性昆虫を材料に上記の目的を達成するための実習を行う。 | 塘 忠顕 福島大学共生システム理工学類 | 2023.9.4~2023.9.8 |
| 30. 長野県植物誌改訂にかかる調査 | 長野県植物誌改定作成にあたり、上田地域の植物分布状況を調べ、さく葉標本を作成して筑波大学菅平高原実験所内のハーバリウムに随時収納する。 | 川上 美保子 長野県植物誌改訂委員会上田地区 | 2023.4.1~2024.3.31 |
| 31. 様々な野生生物を対象とした遺伝的多様性および遺伝構造に関する研究 | 様々な野生生物を対象とした遺伝解析を行い、その遺伝的多様性および遺伝構造を明らかにする。 | 兼子 伸吾 福島大学共生システム理工学類 | 2023.5.1~2024.3.30 |
| 32. 田中健太准教授代表の環境推進費プロジェクト「歴史が生み出す二次的自然のホットスポット:環境価値と保全効果の「見える化」」 | 菅平高原内の森林・草原において、植物と共生する微生物の多様性を探索的に調べ、歴史の古い草原の多様性および生態系サービスの高さをか明らかにする。 | 丑丸 敦史 神戸大学人間発達環境学研究科 | 2023.6.12~2023.11.30 |
| 33. 網翅類の比較発生学的研究 | 系統学的議論の定まらない生物群の系統進化学的理解において、各群のグラウンドプランの構築が可能な比較発生学的アプローチは、有効な方法の一つである。昆虫類のうち、その98%は新翅類というグループが占めているが、この新翅類の初期の爆発的放散に直接由来した多新翅類の一群である網翅類(ゴキブリ目+シロアリ目+カマキリ目)は、昆虫類を理解する上で鍵を握る重要なグループの一つである。以上から、網翅類内の全てのグループを対象とした包括的比較発生学的検証を行い、類内のグラウンドプランの構築と系統進化学的議論の発展を目的に研究を行う。 | 藤田 麻里 慶應義塾大学法学部 | 2023.4.1~2024.3.31 |
| 34. 植物病害が法⾯樹⽊の炭素収⽀に及ぼす影響評価 | 本研究では、植物病害が法面に生育する植物の成長を抑制することを示す。緑化された法面は、維持管理に手間とコストがかかる。本研究では植物―病原菌の炭素収支を計測することで、病原菌が法面植物に対して致死しない程度にその成長を妨げることを示す。生物間相互作用が安定的な植物量を維持し、低コスト管理法となる可能性について探る。 | 増本 翔太 筑波大学生命環境系 | 2023.6.12~2023.12.1 |
| 35. 貧栄養高地環境でアブラナ科植物と共生する内生菌の単離および性状解析 | 貧栄養かつ高地環境で自生するアブラナ科植物の植物組織を採取してそこから内生菌を単離する。その後、内生菌が植物の生存に関わる役割を晝間の研究室内などで明らかにする。 | 晝間 敬 東京大学大学院総合文化研究科 | 2023.6.1~2024.3.31 |
| 36. 植物共生微生物の多様性調査 | 多様な系統の植物と共生する微生物の多様性を明らかにし、森林と草原や、草原の履歴によりそれらが異なるのかを解明する。 | 野口 幹仁 京都大学生態学研究センター | 2023.6.12~2023.6.14 |
| 37. 歴史が生み出す二次的自然のホットスポット:環境価値と保全効果の「見える化」 | これまで考慮されていなかった生態系の歴史を組み込むことで、(1)二次的自然の生物多様性を従来よりはるかに高い精度で現状予測して全国レベルで地図化するとともに、(2)草原の歴史が生物多様性と環境価値に与える効果を全国及びモデル地域で現場検証し、(3)草原の管理実態と消失速度に基づく将来予測によって保全効果を把握する。これによって、二次的自然の生物多様性ホットスポットの分布・環境価値・保全効果を「見える化」する。 | 田中 健太 筑波大学山岳科学センター菅平高原実験所 | 2023.4.1~2026.3.31 |
| 38. 菌類の構造、造形の美しさをガラスで表現する事への探求 | 菌類、変形菌の採集と観察 カビの採集と観察、粘菌の採集と観察したものを展示のためのガラスアート作品のモチーフにするため | 柴田 めいこ 変形菌研究会 | 2023.6.9~2024.3.31 |
| 39. 日本産カノシタ科菌類の分類学的研究 | カノシタ科菌類の試料採集と菌株確立を行い、カノシタ科内の系統樹を作成し、菌根共生の起源を探る。 | 升本 宙 信州大学農学部 | 2023.6.22~2024.3.31 |
| 40. 送粉者を介した異種間の花粉移動と花粉付着部位の種間重複が植物の繁殖におよぼす影響 | 送粉者を共有する植物間では種間花粉移動が起こり、植物の繁殖に悪影響を及ぼす(Morales & Traveset 2008)。これについて、植物が送粉者に花粉を付着させる部位(花粉配置)を一部に集中させることや他種と異なる部位を利用することが種間花粉移動を減らすと推測されている(Armbruster et al 1994, Huang&Shi 2013)が、これらが実際に異種花粉の回避機構として成立しているかについては明確に示されていない。そこで、本研究では、花粉配置の違いが柱頭の異種花粉受粉率を減少させることを、野外実験によって検証する。 | 和田 渚 筑波大学生物学学位プログラム | 2023.7.1~2023.8.31 |
| 41. 日本のアキノキリンソウ属植物を宿主とするColeosporium属菌の種構成の解明 | 日本のアキノキリンソウ属植物上の Coleosporium 属菌はこれまで Coleosporium sp. として扱われてきたが、昨年新潟県で採集された菌を分子系統解析に供試した結果、複数種の Coleosporium 属菌が存在していることが分かった。本研究では、より広い範囲から採集されたアキノキリンソウ属植物上の Coleosporium 属菌を供試し、その種構成を明らかにする。 | 鈴木 浩之 新潟食料農業大学 | 2023.4.1~2024.3.31 |
| 42. 生活史の異なる植物集団の個体群統計パラメーターの推定 | 生活史の異なる植物集団について、生活史段階を不連続にする行列モデルや連続にするモデル群を利用して個体群統計パラメーターを推定する。 | 島谷 健一郎 統計数理研究所 | 2023.4.1~2024.3.31 |
| 43. 野外での倍数体植物の栽培実験 | 植物多様性と環境頑健性の調査 | 爲重 才覚 横浜市立大学 木原生物学研究所 | 2023.7.20~2023.7.21 |
| 44. 植生・表土の歴史に基づく生物多様性ホットスポットの地図化 | 草原植生と表土の継続期間が100年以上ある生物多様性ホットスポットとその消失速度を地図化する。 | 久保田 康裕 琉球大学理学部 | 2023.4.1~2024.3.31 |
| 45. 植物病害が法⾯樹⽊の炭素収⽀に及ぼす影響評価 | 本研究では、植物病害が法面に生育する植物の成長を抑制することを示す。緑化された法面は、維持管理に手間とコストがかかる。本研究では植物―病原菌の炭素収支を計測することで、病原菌が法面植物に対して致死しない程度にその成長を妨げることを示す。生物間相互作用が安定的な植物量を維持し、低コスト管理法となる可能性について探る。 | 篠沢 俊介 筑波大学 | 2023.6.12~2023.12.1 |
| 46. 寄生性ケカビ目菌の研究 | 実験及びデータ整理 | 前川 直人 茨城県林業技術センター | 2023.7.14 |
| 47. 異なる地理的スケールにおけるバイカモ類の集団遺伝学的構造の解明―保全・再生活動への応用― | 水生植物は水圏生態系において、生物多様性への寄与や水質浄化作用など重要な役割を果たしており、バイカモもその一つである。しかし、バイカモは急速な開発や改修、水質汚濁の影響で近年急速に分布を減少しており、適切な管理・保全が必要である。このような種の保全策提案には地域集団の遺伝的多様性、地域集団間の分化やその歴史推定についての情報が重要となり、特に水生植物の場合、地域流域内での水の流れの向きや移動分散を考慮した繁殖様式や遺伝構造の評価も必須である。しかしバイカモではこれらの情報は十分に蓄積されていない。そこで本研究ではバイカモの分布パターンを全国から地域スケールでより詳細に評価すべくバイカモ類を対象に日本全国からサンプルを採取し、広域スケールでの母性遺伝する葉緑体DNA、両性遺伝する核DNAおよびゲノム情報を用いた集団遺伝学的解析を行う。これにより本研究では日本国内の広域スケールでの遺伝情報をもとにした保全単位の地域性や保全優先度の高い地域を提案し、地域スケールでの結果をもとのバイカモの繁殖生態、生活史特性を解明することを目的とする。 | 中城 拓真 筑波大学山岳科学学位プログラム | 2023.4.1~2024.3.31 |
| 48. 信州菅平地域における味噌玉作りの記録と発酵に関わる菌類の同定・生態解明 | 菅平高原を中心に味噌玉を用いた味噌の民間製法を記録することで、消えつつあるウチミソの食文化の資料を後世に残し、その発酵過程で働く菌類の種と動態を究明することで、味噌玉と菌類の関係性を考察し、再現した味噌の官能評価、安全確認を通じてウチミソの食品としての評価を行う。 | 奥村 颯 筑波大学山岳科学学位プログラム | 2023.4.1~2024.3.31 |
| 49. 標高万能植物ミヤマハタザオを用いた生活史遺伝子同定 | 種内で資源配分比・生活史が異なる植物(ミヤマハタザオ)を用いて、資源配分比・生活史と関連がある遺伝子領域を同定し、遺伝学の知見とすることを目的とする。 | 土井 結渚 筑波大学山岳科学学位プログラム | 2023.4.1~2024.3.31 |
| 50. クサカゲロウ腸内酵母はなぜクサカゲロウ腸内から得られるのか? | クサカゲロウの腸内酵母を使った昆虫腸内環境への進出に必要な形質の解明 | 吉橋 佑馬 筑波大学生物学学位プログラム | 2023.4.1~2024.3.31 |
| 51. GPS・UAV・集団ゲノミクスを駆使したツキノワグマの移動分散動態の解明 | GPSバイオロギング・UAVリモートセンシング・集団ゲノミクス技術を駆使して、ツキノワグマの行動生態学的特性の評価および生息密度推定にむけた新たな手法開発に取り組む | 小井土 凜々子 筑波大学生物学学位プログラム | 2023.4.1~2024.3.31 |
| 52. 野外生態系における植物と病原菌の相互作用の探究 | ヤマハタザオに Colletotrichum 属菌を感染させて、野外生態系における植物と菌の相互作用について考察する。 | 鈴木 暁久 筑波大学山岳科学学位プログラム | 2023.4.1~2024.3.31 |
| 53. 変形菌 Arcyria cinerea の種概念についての検討 | 著しい形態的多様性が知られている Arcyria cinerea について、微細形態の観察や分子系統解析を通し、本種に見られる種内変異を解析し、その多様性の解明、種概念についての検討を目的とする。 | 上辰 俊広 筑波大学生物学学位プログラム | 2023.4.1~2024.3.31 |
| 54. 外来魚駆除および在来魚復元が渓流生態系に与える影響 | 外来魚が及ぼしている生態系への影響を明らかにし、外来魚の駆除と在来魚の再導入がどのような生態系影響があるかを調べます。これらを調べた上、効率的で実現可能性が高い在来魚の復元方法を解明します。 | Peterson Miles Isao 筑波大学生命環境系 | 2023.4.1~2024.3.31 |
| 55. Hymenoscyphus fraxineus の子嚢胞子接種によるトネリコ類の抵抗性評価 | セイヨウトネリコ、ホソバトネリコ等の外国産トネリコ類の H. fraxineus 子嚢胞子感染に対する抵抗性を評価する。 | 山岡 裕一 筑波大学生命環境系 | 2023.8.1~2024.3.31 |
| 56. 日本産のヤナギ類に寄生する Melampsora 属菌の中間宿主の探索 | 日本産のヤナギ類に寄生する Melampsora 属菌の中間宿主として、スグリ属植物が活用されているか調査する。 | 山岡 裕一 筑波大学生命環境系 | 2023.8.1~2024.3.31 |
| 57. Polycephalomycetaceae に属する重複寄生性冬虫夏草類に関する分類学的研究 | Polycephalomycetaceae は子嚢菌門フンタマカビ綱ボタンタケ目に属する糸状菌の科であり、広く冬虫夏草類と呼ばれる菌群に含まれる。本科は、他の多くの冬虫夏草類と同様に昆虫寄生性を持つとされる一方で、他種の昆虫寄生菌に重複寄生を行うという特殊な寄生性を示す種を含んでおり、冬虫夏草類における寄生性の進化を考える上で重要な分類群といえる。本研究では、形態学および分子系統学の両側面から科内の系統関係の見直しを行い、Polycephalomycetaceae の分類および冬虫夏草類における重複寄生性の進化に関する新たな知見を得ることを目的とする。 | 須川 元 筑波大学生物学学位プログラム | 2023.4.1~2024.3.31 |
| 58. ヒグラシ族4種の遺伝構造および集団動態の解明 | 国土の約7割を森林が占める日本において、森林生態系の生物多様性に大きく関係する森林性昆虫の環境適応動態を時空間スケールで評価することは重要な課題である。そこで本研究では、時空間スケールで森林性昆虫の環境適応動態を解明するため、生態学的特性の異なるセミ類ヒグラシ族4種を対象に、種間・内の中立および適応的な遺伝的変異や表現形質の地理的変異を評価する。また、森林性昆虫の環境適応は、生息環境を提供する植生の分布変遷にも大きく制限されると考えられるため、生息環境となる森林樹木も考慮した種分布適地の推定を行い、セミ類の未だ不明な生活史特性等の理解も進める。最終的にこれら森林性昆虫の集団遺伝学的動態とその宿主生態系である温帯~冷温帯林の分布変遷の関係を総合的に評価する。さらにこれら手法を応用し、将来の気候変動下における分布予測や集団存続性を評価し、気候変動に関連した森林性昆虫のリスク評価等を行う。 | 湯本 景将 筑波大学生物学学位プログラム | 2023.4.1~2024.3.31 |
| 59. ムカデ綱の糞生菌とその特異性について | ムカデ綱の糞には特異的な菌類が存在する。また、イシムカデ目やオオムカデ目などの、目によって異なる糞生菌相がみられる。ムカデ綱の糞生菌相に影響する事象(消化管構造や餌の種類など)を解明する。 | 清原 広海 筑波大学生物学学位プログラム | 2023.4.1~2024.3.31 |
| 60. キクセラ亜門の分類学及び系統進化学的研究 | 節足動物の腸内や糞上に生息するキクセラ亜門菌類の多様性を明らかにする。また微細構造に基づき、キクセラ亜門の高次系統関係を解明すると同時に、生活様式の進化過程について議論する。 | 李 知彦 筑波大学生物学学位プログラム | 2023.4.1~2024.3.31 |
| 61. 粘菌の生態 | 研究室で粘菌の飼育状況の観察、研究者の方たちと話すこと、粘菌を頂くことが目的です。 | 後小路 葉月 長野県野沢北高校 | 2023.8.10 |
| 62. 植物病原菌 Phyllosticta 属菌の検出、病原性および生態に関する研究 | 園内で観察される Phyllosticta 属菌による病害標本を採集し、病原体の分離、病原性の確認を行うとともに、その防除について検討する。 | 本橋 慶一 東京農業大学国際農業開発学科 | 2023.9.26 |
| 63. 菅平高原地域の菌類調査 | 日本列島の中央部の長野県菅平高原に分布する菌類を調査し、日本の菌類の種多様性の解明ためのデータを収集する。 | 根田 仁 | 2023.10.11~2023.10.13 |
| 64. 森林の菌類多様性の研究 | 国内で十分に調査が進んでいない森林生息性微生物のうち、特に材上の微小菌、およびキクイムシ随伴菌について、種類を調査することで、国内における微生物の生物多様性解明と生物間相互作用ネットワークの解明を目指す。 | 升屋 勇人 森林研究・整備機構森林総合研究所 | 2023.9.27 |
| 65. ブナ葉ぶくれ病線虫の調査 | ブナの葉の特徴的な病巣からブナ葉ぶくれ線虫が分離されるものの、病原体としての断定に至っていない。今回、病徴を示すブナから線虫を採集して季節変遷を追い、病気との関連を調べていく。 | 長谷川 浩一 中部大学応用生物学部環境生物科学科 | 2023.4.4~2024.3.31 |
| 66. 森林におけるツル植物の分布の研究 | 森林におけるツル植物が、幼樹から成木になるまでの間にどのように成長し、周りの環境の影響を受けているのかを明らかにする。 | 鈴木 元康 筑波大学山岳科学学位プログラム | 2023.10.15~2024.3.31 |
| 67. シラウオタケ地衣体上に菌核を形成する地衣生菌に関する分類学的研究 | シラウオタケ地衣体上に菌核を形成する地衣生菌の分類学的所属および生態についての知見を得る。 | 森山 貴登 京都大学農学部森林科学科 | 2023.9.11~2024.3.31 |
| 68. 菌類の構造、造形の美しさをガラスで表現する事への探求 | 粘菌、好雪性粘菌の採集と観察 | 柴田 めいこ 変形菌研究会 | 2023.10.11~2024.3.31 |
| 69. フェノロジー定点カメラシステム設置案に関する事前視察 | アカマツ林タワーなど、フェノロジー定点カメラシステムを設置するのに適当な場所の候補を視察・検討する。 | 奈佐原 顕郎 筑波大学生命環境系 | 2023.10.25 |
| 70. 気候変動下の森林保全に向けた森林樹木の標高に沿った環境適応および平行進化の解明 | ブナ属、ナナカマド属、ビャクシン属樹種を対象に、垂直方向に着目した遺伝構造および地域集団形成時期等の集団動態を推定し、さらに垂直方向、特に高標高に適応した遺伝子を検出し、これら遺伝子の種や属を超えた平行進化の実態を明らかにする。 | 津田 吉晃 筑波大学山岳科学センター菅平高原実験所 | 2023.4.1~2024.3.31 |
| 71. 生態・遺伝子・地質・地域特性情報に基づく長野県における野生動物管理の提案 | 長野県内のシカの遺伝構造を解析すべく、長野県環境保全研究所で冷凍保管されているシカ・サンプルを整理し、菅平高原実験所にサンプルを移動し、DNA抽出および遺伝解析実験を行う。 | 高木 俊人 福島大学共生システム理工学類 | 2023.4.1~2024.3.31 |
| 72. 針葉樹の毬果に発生する菌類の研究 | 針葉樹の毬果に特異的に発生する菌類について、なぜ、このような顕著な宿主特異性が生じるのか、生態学的な解明を試みる。 | 萩本 宏 日本菌学会 | 2023.11.1~2024.3.31 |
| 73. ヤマトイシノミモドキ類(イシノミ目・イシノミ科)の配偶行動の研究 | ヤマトイシノミモドキ類(イシノミ目・イシノミ科)の配偶行動の観察、および配偶行動に関連する雌雄の外部生殖器の外部形態の観察に基づき、イシノミ目における配偶行動様式のグラウンドプランを議論するとともに、昆虫類における配偶行動様式の系統進化シナリオを考察する。 | 武藤 将道 名城大学農学部生物資源学科 | 2023.4.1~2024.3.31 |
| 74. 植物の地上部地下部形質と生態系サービスの関係解析 | 左記の研究テーマのために、植物の根の形質測定を実施する。 | 黒川 紘子 森林研究・整備機構森林総合研究所 | 2023.12.1~2023.12.2 |
| 75. 変形菌の生理生態調査 | 特徴的なライフサイクルを有する変形菌の各ライフサイクル(子実体や変形体)における局在を解明する。 | 梅澤 和寛 静岡県立大学 | 2024.3.13~2024.3.15 |
| 76. 六脚類の頭部内骨格の進化的変遷 | 昆虫はそのコンパクトな頭部に刺激受容と情報統合、摂食という生存に不可欠な複数の機能を同時に備える優れたボディプランをもち、これらの機能を洗練させることによりあらゆる環境に適応、多様化してきた。有翅昆虫の頭部内にみられる「幕状骨」は、外胚葉性陥入の融合により形成される幕状の強固な骨組みで、複眼や脳を格納する大きな頭蓋の土台であるとともに、筋肉の付着点として大顎・小顎の運動機能を支えている。本研究は、発生過程、特に昆虫頭部内骨格の脱皮時の形態変化に着目することにより、幕状骨をはじめとする頭部内骨格に起きてきた段階的イノベーションと、昆虫類の進化的成功との関連を明らかにする。 | 福井 眞生子 愛媛大学大学院理工学研究科 | 2024.3.1~2024.3.31 |
| 77. 好雪性粘菌の調査 | 好雪生粘菌を環境DNAで検出するため | 五條 麟太郎 東京理科大学創域理工学部生命生物科学科 | 2024.3.13~2024.3.15 |
| 78. 山岳地域における遺伝的多様性データベース構築にむけた先端研究教育拠点の形成 | JSPS研究拠点形成事業(アジア・アフリカ学術基盤形成型B)”山岳地域における遺伝的多様性データベース構築にむけた先端研究教育拠点の形成”のセミナーの一環として、菅平高原実験所内でエクスカーションを行う | 津田 吉晃 筑波大学山岳科学センター菅平高原実験所 | 2024.3.7~2024.3.7 |