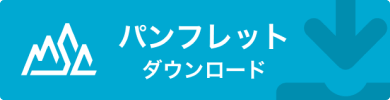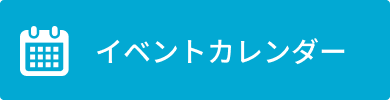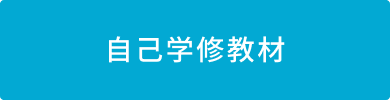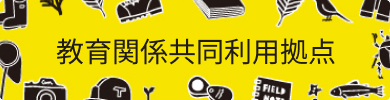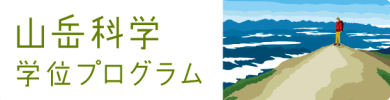2025年度研究課題一覧
随時更新しています。
| 研究課題名(受付順) | 概要 | 研究代表者・所属 | 実施期間 |
|---|---|---|---|
| 1. どんぐりの企画展用映像撮影(リス・カケスのどんぐり利用、植生のドローン撮影)、どんぐり展示用サンプルの採集(ミズナラの果実等) | ミュージアムパーク茨城県自然博物館で開催予定のどんぐりの企画展の資料を集めるため | 伊藤 彩乃 茨城県自然博物館 | 2025.4.1~2026.3.31 |
| 2. 変形菌の生理生態調査 | 融雪期にみられる好雪性変形菌の生態を解明し、冬季における森林の腐食機構の解明を目指す。 | 梅澤 和寛 静岡県立大学 | 2025.4.18~2026.3.31 |
| 3. 本州中部冷温帯の半自然草原をはじめとする植生の違いにともなう植物体地下部の純一次生産(BNPP)の変化 | 細根の純一次生産(BNPP)は草原生態系および森林生態系の純一次生産の1/3以上占めるとされるが、定量化が難しいBNPPの知見は不足している。特に、植生の違いで土壌有機炭素量(SOC)は異なるものの、SOCに寄与するBNPPのターンオーバーについて不明点が多い。本研究は、植生の違いによるBNPPの変化パターンとメカニズム解明を目的とする。特に、優占種の違いによるBNPPの変化を定量化するとともに、それによる土壌圏の炭素動態の変化を考査する。 | 西平 貴一 筑波大学大学院環境学学位プログラム | 2025.4.9~2026.11.30 |
| 4. Hymenoscyphus fraxineus の子嚢胞子接種によるトネリコ類の抵抗性評価 | セイヨウトネリコ、ホソバトネリコ等の外国産トネリコ類の H. fraxineus 子嚢胞子感染に対する抵抗性を評価する。 | 山岡 裕一 筑波大学生命環境系 | 2025.4.1~2026.3.31 |
| 5. 昆虫(無脊椎動物)嗜好性線虫の分類と多様性 | 昆虫(無脊椎動物)嗜好性線虫の分類と多様性、生態的関係を基礎研究として調査する。また、この過程で得られた特殊な生理、生態的特徴を持つ種類に関しては、モデル(研究材料)として、他の研究分野への応用を行う。 | 神崎 菜摘 森林総合研究所関西支所 | 2025.5.1~2026.3.31 |
| 6. 菅平盆地で形成される接地逆転層「冷気湖」形成時に、気温と風の分布や変動で見られる特徴的な大気現象の解明 | 盆地底と菅平高原実験所との気温の差から求めた大気安定度指標を用いて、気温と風の変動の特徴を明らかにする。また、この大気安定度は、夜間冷却の強さと大気中の物質輸送過程に関係することから、ここで求めた大気安定度の指標を用いて、気温と風の変動から、盆地内の夜間冷却と夜間の気温形成のメカニズムと安定層内における熱やエネルギーと物質輸送過程に関する知見を得る。これらから、菅平盆地など盆地状の地形をもつ地域で見られる特徴的な気象と気候の特徴を明らかにする。 | 鳥谷 均 NPO法人圃場診断システム推進機構 | 2025.4.1~2026.3.31 |
| 7. 好雪性変形菌ならびに好雪変形菌に寄生する原始的な寄生菌の研究 | 菅平菌類相調査の一環で、変形菌相を明らかにする。特に、融雪時に限定的に発生する好雪性変形菌ならびに好雪性変形菌に寄生するロゼラ門の寄生菌について探索する。菅平高原実験所および周辺のフィールドでこれらの菌の採集を行い、持ち帰り顕微鏡観察により検討する。 | 矢島 由佳 室蘭工業大学大学院工学研究科 | 2025.4.1~2026.3.31 |
| 8. 菅平高原実験所内の変形菌類相 | 菌類相調査の一環、ならびに、日本変形菌研究会の会活動としての本邦の変形菌相の解明の一環として、菅平高原実験所内の変形菌相を明らかにする。特に、今回は、融雪時に限定的に発生する好雪性変形菌の子実体を採集して、種同定をする。 | 出川 洋介 筑波大学山岳科学センター菅平高原実験所 | 2025.4.1~2026.3.31 |
| 9. カラマツ林の葉面積指数の連続観測による葉群フェノロジーの年次変化の評価 | 2018年12月に気候変動適応法が施行され、長野県は2019年4月に信州気候変動適応センターを設置した。信州気候変動適応センターは、気候変動の実態把握、予測、影響評価を行うことで、地域の気候変動適応策を促進することが重要な課題となっている。本研究では気候変動が信州カラマツに及ぼす影響を評価するため、カラマツ林の葉面積指数と気温の連続観測を継続し、近年の急激な気温上昇に伴う葉群フェノロジーの変化を明らかにすることを目的とする。 | 栗林 正俊 長野県環境保全研究所 | 2025.4.1~2026.3.31 |
| 10.菅平変形菌ワークショップ | 顕微鏡観察により、菅平高原および長野県、群馬県ほか各地で採集した変形菌の標本の種同定を行う。併せて、菅平菌類相調査時の標本整理活動も実施する。 | 姉﨑 智子 群馬県立自然史博物館 | 2025.4.9~2026.3.10 |
| 11. 植生再生過程における植物-送粉者、植食者多様性の変化 | 本研究では、歴史の異なる草原(新草原・古草原)の送粉・植食ネットワークの状態を比較し、以下の予測を検証する。新草原は、古草原に比べ、(1)送粉者および植食性昆虫の多様性は低くジェネラリスト化する。また、新草原では、(2)造成時期が古い場所ほど、虫媒植物の種・機能的多様性が高くなり、ネットワークはよりスペシャリスト化している。 以上の仮説を検証することを目的とする。 | 平山 楽 神戸大学人間発達環境学研究科 | 2025.5.19~2025.10.31 |
| 12. 菅平菌類相調査 | 菅平高原実験所を中心とした菅平高原の菌類相を解明すること。 | 出川 洋介 筑波大学山岳科学センター菅平高原実験所 筑波大学生命環境系 | 2025.4.1~2026.3.31 |
| 13. 昆虫類の比較発生学的研究 | 昆虫群を比較発生学の観点から検討し、昆虫類の高次系統、グラウンドプランの構築を目指す。 | 町田 龍一郎 | 2025.4.1~2026.3.31 |
| 14. 木本性つる植物と樹木の成長戦略の違いと気候に応じた変遷 | 樹木に巻き付き、その特性から少ない幹への投資で林冠に多くの葉をつけ、樹木の成長を阻害しながら繁殖する木本性つる植物は、森林の炭素蓄積を減少させる存在であるとして、大気中の二酸化炭素を増加させる危険性があり、また木本性つる植物のバイオマスは近年増加しているという研究もあり環境問題の一つとなっている。こうした木本性つる植物に関する研究は熱帯林では多くあり、葉の形質、水分戦略などが樹木と比較され、どのように樹木に対してアドバンテージを取っているかということが解明されているが、現状熱帯林以外の亜熱帯、温帯、亜寒帯、寒帯林では研究の数が少なく、日本での分布などは研究がされているが葉の形質や戦略に関することはあまり調べられていない。当研究ではそれらを調べ、日本のそれぞれの気候において木本性つる植物がどのような戦略で森林で生育し、この先に訪れる気候変動に対してそれぞれの森林における木本性つる植物がどういった変化をする可能性があるのかということを考察する。 | 坂上 悠馬 京都大学大学院農学研究科 | 2025.4.1~2026.3.31 |
| 15. クロサンショウウオの卵に共生する緑藻の系統分類学的研究 | クロサンショウウオの卵に共生する緑藻について、その形態を明らかにする。 | 成田 紗由美 筑波大学大学院理工情報生命学術院 | 2025.4.17~2026.3.31 |
| 16. ヘビの臭腺分泌物による捕食者誘引効果の野外検証 | 申請者らが提唱した「呪い仮説」は、動物が防御のために放出する分泌物が、捕食者に付着し、その捕食者の天敵(高次捕食者)を誘引するというものである。室内実験では、シマヘビの臭腺分泌物が、その捕食者(鳥類など)の天敵にあたるアオダイショウ成体を誘引することが示され、この仮説が支持された。本研究では、この実験室で確認されたシマヘビ臭腺分泌物によるアオダイショウの誘引効果が、より複雑な野外環境においても実際に生じるのかを検証する。さらに、分泌物が付着した対象の捕食リスクを増加させるのかも直接検証する。 | 秋元 洋希 早稲田大学大学院先進理工学研究科 | 2025.5.1~2025.6.30 |
| 17. ゴキブリ目および網翅類の比較発生学的研究 | 系統学的議論の定まらない生物群の系統進化学的理解において、各群のグラウンドプランの構築が可能な比較発生学的アプローチは、有効な方法の一つである。昆虫類のうち、その98%は新翅類というグループが占めているが、この新翅類の初期の爆発的放散に直接由来した多新翅類の一群であるゴキブリ類は、昆虫類を理解する上で鍵を握る重要なグループの一つである。以上から、ゴキブリ類内の全てのグループを対象とした包括的比較発生学的検証を行い、類内のグラウンドプランの構築と系統進化学的議論の発展を目的に研究を行う。 | 藤田 麻里 筑波大学山岳科学センター菅平高原実験所 | 2025.4.1~ 2026.3.31 |
| 18. | 取り下げ | ||
| 19. 膜翅目昆虫原始系統群における翅原基の後胚発生様式に関する比較発生学的研究(昆虫綱:膜翅目:広腰亜目) | 昨年に引き続き、膜翅目昆虫の中でも最も原始的な系統群に位置付けられる「ヒラタハバチ科 Cephalcia sp.」をモデル材料とし、完全変態昆虫における翅原基形成様式の初期進化を明らかにすることを目的として、本種の翅原基の後胚発生様式を調査する。 | 新津 修平 東京都立大学大学院理学研究科 | 2025.6.4~2025.6.11 |
| 20. カンアオイ属ウスバサイシン節国内種の遺伝的多様性研究 | ウスバサイシン節が属するウマノスズクサ科カンアオイ属は東アジアを中心に100種以上が知られ (Shin et al., 2015)、多様性の高い形態・生態や進化史を持つ分類群である。しかし本属を対象とする先行研究の多くではカンアオイ節を用いており、ウスバサイシン節を主とした事例は多くない。日本産ウスバサイシン節は7種中5種がレッドリストに記載されている希少な存在であり、生息地の開発のみならず盗掘やシカ等の野生動物による食害の影響の深刻化が危惧されている。また、漢方薬・細辛の材料としての利用やヒメギフチョウの食草であることなど、多様な生態系サービスの供給者でもある。そこで本研究ではネイチャーポジティブ実現に寄与するウスバサイシン節の保全策社会実装を最終目標とし、本節の適切な保全推進に必要な科学的知見の蓄積を目的に研究を行う。 | 新 真澄 筑波大学理工情報生命学術院 | 2025.5.7~2025.5.9 |
| 21. ケラ Gryllotalpa orientalis Burmeister,1839の発生学的研究(昆虫網・直翅目・ケラ科) | 昆虫類は全動物種のおよそ75%を占める巨大で多様性に富む動物群である。昆虫類の系統進化の理解において、その98%を占める新翅類は大変重要なグループであり、この新翅類の初期の爆発的放散に直接由来した多新翅類の理解は極めて重要である。しかしながら、多新翅類の分岐は深く、各目の特殊化も著しいため、類内の系統進化学的理解は困難なものとされ、今なお議論の余地が残されている。比較発生学的アプローチはこのような系統進化学的議論において有効な方法の一つであるが、多新翅類の理解に向けて、まずはその一群である直翅目を対象とした包括的な比較発生学の第一歩として、ケラ科のケラ Gryllotalpa orientalis Burmeister,1839 を材料に、発生学的知見および生物学的知見の充足を目指し研究を行う。 | 芝 寧々子 筑波大学生物学類 | 2025.4.1~2026.3.31 |
| 22. 山岳地域の訪問者の非意図的な種子導入に関わる要因 | グローバリゼーションによる人間活動の増加によって外来植物の侵入の規模や速度が拡大している。人間は移動性の向上と人口の増加により媒介者として高い能力を持ち、非意図的な導入の侵入経路は衣類や車両を介した導入など多岐にわたる。しかし外来植物は効果的な対策により防除が可能であり、最も費用対効果が高いとされる導入の未然防止が求められる。 外来植物の種子の導入量の規定には、侵入プロセス(媒介者への侵入、輸送、脱落)の各段階で異なる要因の影響を受けることが明らかになっている。媒介者への侵入段階では訪問者への種子の付着の要因、輸送段階では除去行為の有無、脱落段階では除去されずに輸送された種子の量が関係する。侵入初期段階である付着から脱落の段階に着目した研究は、侵入後期にあたる定着から拡散の段階の研究より少ない。外来植物の侵入の未然防止には、経験的データを用いた侵入プロセスの実態の把握が必要である。 本研究の目的は、外来種侵入防止に向けて効果的な保全を行うために、導入する種子の量を規定する上での重要な侵入プロセスを理解することである。 | 小林 千夏 東京農工大学農学府 | 2025.5.14~2025.5.16 |
| 23. 降積雪を中心とした気象測器の設置環境と測定値の関係に関するデータ収集と調査 | 既存の気象観測に含まれる測定値に対する観測点周辺環境の影響を評価するための基礎資料の収集 | 西森 基貴 農研機構・農業環境研究部門 | 2025.4.1~2026.3.31 |
| 24. 菅平高原実験所構内の微小菌類相の解明 | 2033年の菅平実験所の100周年に向けて進められている菅平菌類相調査の一環として、菌類の中でも多様性の解析が遅れている微小菌類、いわゆるカビの仲間に関する集中調査をする。本調査は研究者や学生のみならず、市民科学的要素も取り入れ、菌類に関心のある一般市民も参加をすることにも大きな意義がある。このため、菅平菌学研究室のメンバー、菌類の各分類群、生態群の専門家に加え、菅平ナチュラリストの会・菌類班のメンバーや菌類に関心を持つ一般市民として、特に、微小菌類(カビ類)に関心を持つメンバーも参加して、微小菌類相の解明を目指す。 | 柴田 めいこ 日本変形菌研究会 | 2025.5.12~2026.3.31 |
| 25. サワラ、ビャクシン類およびウラジロノキ、カマツカ等のバラ科植物上での Gymnosporangium 属菌(さび病菌)の発生調査と試料の採取 | セイヨウトネリコ、ホソバトネリコ等の外国産トネリコ類の H. fraxineus 子嚢胞子感染に対する抵抗性を評価する。 | 山岡 裕一 筑波大学生命環境系 | 2025.4.1~2026.3.31 |
| 26. 根子岳周辺の植生調査 | 根子岳周辺の標高による植生分布を把握する。 | 永井 千尋 筑波大学生物学類 | 2025.4.1~2026.3.31 |
| 27. カケスの種子散布によるアカマツーミズナラ林の遷移に関する研究 | 調査対象としている区域は、かつての牧草地が、草刈りをやめたことによって、アカマツが生え、次第に、アカマツ林として発達してきた場所である。そのアカマツ林内に、ある時から、ミズナラの実生が育ち始め、やがて、若木へと成長する過程の記録が、1970年代から残っている(参考文献:「里山の植物生態学」加藤順・林一六 2023全国農村教育協会)。このミズナラの実生や若木は、演習林内に生息するカケスの貯食行動によるものと推測されている(アニマ 140号 ミズナラ林を作るのは誰か?中村浩志 1984)。今回、この貴重な遷移の調査記録を引継ぐ形で、現在の成長量の調査を行う。また、新たなミズナラの実生を調査することで、カケスが貯食している行動域についても調査する。 | 藤原 英史 株式会社ドキュメンタリーチャンネル | 2025.6.2~2025.6.4 |
| 28. 景観管理・景観ゲノミクスに着目したツキノワグマの保護管理に関する研究 | 本研究課題では、アーバン化リスクの早期評価および抑止を念頭においたツキノワグマ(以下、クマ)地域集団の新しい保護管理手法の提案を目的として、A) 中部山岳域におけるクマ地域集団の景観ゲノミクス、B)ゲノミクス(SNP・SSR)データとGPS行動データとのゲノムワイド関連解析(GWAS)、C)人里およびその周辺におけるクマ個体間関係の解明、D)質問紙調査によるクマ軋轢問題の評価に取り組む。 これらの結果から、アーバン化関連要因を遺伝的特徴から評価するとともに、景観ゲノミクス的解析にて推定された集団遺伝的構造および遺伝子流動の方向性から、効果的な地域集団・個体モニタリング方針を提案する。これに加え、人文地理学的調査から、地域社会のクマ保護管理に対する意識を調査し、今後の管理方針について利害関係者間(行政・民間・研究者)での合意形成を目指す。 | 松本 拓馬 筑波大学大学院農学学位プログラム | 2025.4.1~2026.3.31 |
| 29. シカ被食リスクに着目した希少植物の保全遺伝学的研究:北アルプス周辺における生物多様性保全に向けて | 本研究の目的は、ニホンジカにおける被食率の高い高山・亜高山植物、山麓に生育する木本の集団遺伝構造を解明し、遺伝的多様性や固有性を明らかにすることである。得られた結果を元に保全優先度の高い地域集団のランク付けを行い、保全対策を提案する。 | 澤田 佳奈 筑波大学大学院山岳科学学位プログラム | 2025.4.1~2026.3.31 |
| 30. 古草原ー森林ー新草原への植生の変化が植物根を含めた土壌炭素量に及ぼす影響 | 菅平高原、中部山岳地域を中心とした草原・森林・草原のフィールドにおいて、層位の対応を確認しながら根系量・炭素量の深度分布を明らかにすることを目的とする。 | 加藤 拓 東京農業大学 | 2025.6.25~2026.3.31 |
| 31. 山岳域での生物多様性長期連続観測 | 日本の主要山岳域における気象・植生・動物の長期連続観測の整備を目標とし、各山域に観測機器を設置する。観測データを用いて山岳生態系の現状を把握するとともに、各山域での自然保護活動の評価を生物多様性指標を用いて科学データとして示す。 | 松永 寛之 筑波大学山岳科学センター菅平高原実験所 | 2025.4.1~2026.3.31 |
| 32. タケ類寄生菌の採集 | タケ類に寄生する菌類の分類学的研究 | 白水 貴 三重大学 | 2025.4.1~2026.3.31 |
| 33. 植物の地上部地下部形質と生態系サービスの関係解析 | 左記の研究テーマのために、植物の根の形質測定を実施する | 黒川 紘子 京都大学農学研究科 | 2025.5.1~2026.3.31 |
| 34. 実習科目名「自然環境調査法」:ススキ草原と夏緑広葉樹林に生息する生物を対象とした、生物調査法に関する実習 | 生物の採集法、観察法、標本作製法、同定法を実地で学ぶことが目的である。菅平高原実験所内の草原植物、草原性および森林性昆虫を材料に上記の目的を達成するための実習を行う。 | 塘 忠顕 福島大学共生システム理工学類 | 2025.8.18~2025.8.22 |
| 35. 気候変動下における亜高山帯樹木の環境適応動態の解明 | 生物のゲノムに存在する“動くDNA”であるトランスポゾンは、新たな遺伝的多様性を創出し、進化に寄与すると考えられている。樹木は百年単位の長命性を持ち、一世代でも複数回の環境変動に直面する可能性が高いにも関わらず、長い進化生物史の中で世界各地に分布してきた。よって、森林樹木の環境適応にもトランスポゾンが深く関わっていると考えられるが、森林樹木のトランスポゾンに関する研究は未着手である。そこで本研究では、気候変動の影響を受けやすい亜高山帯樹木を対象に最新ゲノミクス解析を行い、トランスポゾンの環境適応における役割を明らかにし、さらに種を越えたトランスポゾンの平行進化の解明を目的とする。 | 播本 泰知 筑波大学大学院生物学学位プログラム | 2025.4.1~2026.3.31 |
| 36. 大規模データを活用した温暖化に対する生物群集の分布応答評価 | 地球規模の気候変動に呼応した生物の分布移動により、生物群集の特性がどのように変化しているのか、大規模な在データから検出するモデルを構築し、多様な生物群集に適用する。 | 關 岳陽 筑波大学大学院生物学学位プログラム | 2025.4.1~2026.3.31 |
| 37. 子嚢菌門ラブルベニア綱の分類・生活史・培養に関する研究 | 本菌群の形態観察、分子系統解析、培養試行などを通じて、子嚢菌門ラブルベニア綱の多様化した要因を解明する | 田中 凌太 筑波大学大学院生物学学位プログラム | 2025.4.1~2026.3.31 |
| 38. 長野県上田市周辺における微小〜小型菌類相の解明及び分子系統的位置について | 長野県上田市周辺に発生する菌群の形態観察、分子系統解析、培養試行などを通じて、本地域の菌類の多様性を解明する | 嶋﨑 拓 筑波大学大学院山岳科学学位プログラム | 2025.4.1~2026.3.31 |
| 39. 植物種間の花色コントラストを空間的な混在度および報酬差から予測する | 同じ場所で同時期に咲く植物種の間では、しばしば送粉者を介して、繁殖成功を妨げる異種間花粉移動が起こる。これを防ぐ戦略の一つとして提唱されてきたのが、他種と互いに異なる花色をもつことによる、送粉者の定花性(同じ種や特徴が似た花ばかりを連続して訪れる習性)の強化である。しかし、植物群集における花色の多様性を調べたこれまでの研究からは、この予測を支持する一貫した証拠は得られていない。そこで、本研究では「花色の違いが双方の植物種にとって有利になるのは、互いに空間的に混ざり合って生育し、かつ花蜜などの報酬量が同等な場合に限られる」という仮説に着目し、フィールド調査を実施する。 | 高木 健太郎 筑波大学大学院生物学学位プログラム | 2025.6.16~2025.6.17 |
| 40. 草原の維持管理における社会的支援獲得に向けた環境価値情報の効果 | 多様なステークホルダー(利用者・管理者・住民・自治体・企業)が、歴史の古い草原の生物多様性や環境価値のうち、どの科学的知見を提示することで草原の保全動機を喚起し社会的支援(資金・労力)の獲得に有効かを解明する。 | 冨高 まほろ 筑波大学山岳科学センター菅平高原実験所 | 2025.4.1~2026.3.31 |
| 41. 気候変動下における国内外来種ヌマガエルの集団ゲノミクスおよび分布拡大リスク評価 | 遺伝情報と環境要因の統合解析による国内外来種ヌマガエルの分布拡大経路・要因の解明、気候変動が本種の分布拡大に与える影響の評価を行い、最終的に将来的な拡大リスクの予測と保全管理策の基盤情報を構築することを目的とする。 | 鎗田 めぐ 筑波大学大学院農学学位プログラム | 2025.4.1~2026.3.31 |
| 42. 長期にわたって維持されてきた草原に生息する植物種の根系量と防災機能 | これまでに、草原の継続期間とともに生物多様性が高くなっていることが分かっている。また歴史の古い草原は、生物多様性だけでなく、様々な生態系サービスが高い可能性がある。その中で私は、歴史の古い草原に高い斜面防災機能がある可能性に着目した。歴史の古い草原には根系が大きい植物種が多く、私はこれが斜面防災機能を高めているのではないかと考えた。そこで私は、歴史の古い草原の斜面防災機能について理解を進めることを目的として、古い草原は新しい草原や森林に比べて根系量が多いという作業仮説の立証するため、根系量が歴史の古い草原で多いのかを、同一地域の新しい草原や森林との比較によって検証した。 | 寺嶋 悠人 筑波大学大学院山岳科学学位プログラム | 2025.4.1~2026.3.31 |
| 43. 北アルプスにおけるニホンジカの集団遺伝学的動態 | 集団ゲノミクス解析を用いて、北アルプスへの分布拡大が進むニホンジカ集団の遺伝的多様性を把握し、長野県内外および北アルプス周辺地域における遺伝構造の関係性を解明する。得られた知見をもとに、北アルプスにおける有効な個体数管理手法の提案を目指し、森林生態系の保全に資することを目的とする。 | 熊瀬 卓己 筑波大学大学院山岳科学学位プログラム | 2025.4.1~2026.3.31 |
| 44. 長野県上田市の農業用ため池堰堤の耐震工事前後における希少植物の追跡 | 古くは数百年前から続くため池。草刈りや火入れなど、人の営みによって維持管理され、希少植物の生息地となってきた。 しかし、東日本大震災、菱日本豪雨を受けて、農業用ため池の防災工事が進んでいる。工事は堰堤を掘削する必要があり、生息する植物への影響が懸念される。そこで指導教官の提案により、5年ほど前から希少植物へ配慮した工法を採用してきた。 本研究においては、追跡調査を行い、植物配慮工法がどの程度有効なのかを検証する。 | 市野 祥子 筑波大学大学院山岳科学学位プログラム | 2025.4.1~2026.3.31 |
| 45. 継続期間の異なる草原と森林の根系量、根系強度と斜面防災機能の解明 | 草原の継続期間や履歴による違いが植物の地下部を構成している根系にどのように影響を与えているか研究を行い、長期にわたって古い草原に生息する植物の生存戦略、草原の斜面防災機能について明らかにしていくことを目的としている。 | 入江 瑞生 筑波大学大学院山岳科学学位プログラム | 2025.4.1~2026.3.31 |
| 46. 管理方式及び歴史性が異なる水田における植生及び植食性昆虫相の差異の解明 | 本研究では、水田の半自然草原の歴史(成立年代)によって植物と植食性昆虫(鱗翅目・直翅目)の多様性が高まるのかを明らかにするとともに、そうした歴史のポテンシャルは、どんな管理方式・環境要因で発揮されるのかを明らかにする。そして、生物多様性を高める水田の管理方式を導き出すことで農業生態系における環境保全の一助を担うことを目的とする。 | 漆崎 壮太 筑波大学大学院山岳科学学位プログラム | 2025.4.1~2026.3.31 |
| 47. 菅平菌類相調査における大型菌類 (macrofungi) の解析 | 菅平菌類相調査の中で、特に、大型の子実体を形成する大型菌類(いわゆるキノコ)についての検討を行い、実験所内の菌類相全体の考察を行うこと。 | 佐々木 秀晃 筑波大学生物学類 | 2025.4.1~2026.3.31 |
| 48. 真菌類における節足動物の腸内生の進化過程の解明 | 真菌類において節足動物の腸管内で付着生活を行う生活様式はキクセラ亜門にのみ見られる独自の生態であり、その生活様式の進化過程は謎に包まれている。本研究では腸内への付着構造に着目し、キクセラ亜門の微細構造を観察・比較することで、キクセラ亜門内の系統関係の再構築を行い、腸内生の進化過程を明らかにする。 | 李 知彦 筑波大学山岳科学センター菅平高原実験所 | 2025.4.1~2026.3.31 |
| 49. ナス属植物の繁殖生態に関する研究 | 菅平湿原に生育するオオマルバノホロシの繁殖生態の調査のため、採集および観察を行う。 | 土松 隆志 東京大学大学院理学系研究科 | 2025.7.22~2025.7.23 |
| 50. 菅平高原実験所構内の盤菌相の解明 | 実験所構内に生息する盤菌類(広義)のフロラを解明すること。 | 細矢 剛 国立科学博物館 | 2025.4.1~2026.3.31 |
| 51. 菅平高原実験所構内の植物病原菌相の解明 | 手法:植物に寄生する菌類を探索し、採集。 押し葉標本を作成し保管する。 その際、現場写真、検鏡写真、菌についての記録を作成し、データ登録する。 | 赤堀 千里 神奈県立生命の星・地球博物館菌類ボランティア | 2025.4.1~2026.3.31 |
| 52. 動物死骸の分解に関わる菌類の調査 | 動物死骸の分解過程において発生する菌類を分類同定し、その生態について調査すること。 | 金谷 一輝 筑波大学大学院山岳科学学位プログラム | 2025.4.1~2026.3.31 |
| 53. 飛来昆虫が運ぶ人糞の二次糞生菌相の調査 | 野外でのヒトの分解についての理解を深めることを目的とする。ヒトの糞は菌類や動物によって分解されると考えられるが、その詳細なプロセスを解明した先行研究は無い。ヒトの糞上に発生する菌類の胞子の由来は経口的とは考えられないことから、発生してくる菌はいずれも二次糞生菌であると推定される。二次糞生菌の中でも、飛来昆虫によりもたらされる菌は、比較的、糞の分解に適応したものであろうという仮説が考えられることから、この検証を行う。 | 平田 洋祐 筑波大学生物学類 | 2025.4.1~2026.3.31 |
| 54. 異なる時空間スケールにおけるツキノワグマの移動分散・集団動態の解明 | 行動追跡・血液検査・遺伝情報解析を駆使したツキノワグマの生態・遺伝学的パターンの評価を通して、ツキノワグマの移動分散・集団動態を総合的に解明する。 | 小井土 凜々子 筑波大学大学院生物学学位プログラム | 2025.4.1~2026.3.31 |
| 55. 歴史の古い草原における生態系の多機能性の規定要因の解明 | 草原における継続年数の違いが、植物や土壌微生物の多様性・組成を介してどのようなメカニズムで生態系の多機能性に影響を与えるのかを明らかにする。 | 野中 駿 横浜国立大学環境情報学府 | 2025.7.13~2025.10.31 |
| 56. 菅平高原実験所構内のコウヤクタケ類の多様性の解明 | 菅平高原実験所構内のコウヤクタケ類について、フィールド調査と顕微鏡観察、培養検討、分子系統解析などを進めて、多様性を解明する。 | 前川 二太郎 日本菌学会 | 2025.4.1~2026.3.31 |
| 57. 海洋生態系保全に向けた、地球温暖化で分布移動する魚類の集団ゲノミクス動態の解明 | 地球温暖化による魚類への影響予測を最終目的として、カワアナゴ科魚類を対象に集団遺伝学、生物地理学、生態学、形態学および海洋物理学的研究を行い、過去から現在にかけての分布変遷、分散過程、遺伝構造および集団動態の歴史を解明する。 | 山川 宇宙 筑波大学大学院生命環境科学研究科 | 2025.4.1~2026.3.31 |
| 58. Monitoring bee populations to contribute to a citizen-science database for Japanese bumblebees | Recently, insect declines are being reported around the world, and there is worry that declines in pollinator populations and diversity may affect global food security. Much research into pollinators and their potential stressors has progressed in North America and Europe, but Asia and Africa have fallen behind. This research proposal presents an opportunity to help shed light on bee diversity. Nagano is considered as one of the most diverse regions for bee diversity in Japan, so we would like to sample at Sugadaira. Manual collection of bees will be carried out using a sweep net, flowers will be observed using timelapse cameras (installed for several hours by planting a stake in the ground and fixing the camera to it), seeds of flowering plants will be collected, and data for habitat and flora will be recorded. | Mohamed Shebl Graduate School of Life Sciences, Tohoku University | 2025.7.22~2025.7.25 |
| 59. 日本各地の蟻相調査とクシケアリ類の比較生態調査・観察 | 実験所構内の各植生ごとの蟻類の被度指数を測定し、蟻相のタイプを査定する(昨年の継続調査)。所内全体の蟻相調査およびクシケアリの生態調査も行なう。 | 近藤 正樹 近藤蟻蜘蛛研究所 | 2025.6.23~2025.6.26 |
| 60. 菌えいを餌資源とする昆虫は菌えいのどこを同化して、どのように菌えいに宿主転換・拡大を起こしているのか | 菌えいとは菌類が植物体の一部を肥大成長させた菌基質・植物基質の両方を有する構造物である。 | 曲 雅慧 早稲田大学大学院先進理工学研究科 | 2025.6.24~2025.6.26 |
| 61. 様々な生態系に分布する様々な種の生物・遺伝的多様性研究および山岳科学教育・研究の国際化 | 様々な生態系に生育する様々な生物種の進化生物学史を明らかにし、気候変動下の生態系管理・保全に活用する。また日本~世界を結ぶ山岳科学の教育・研究を展開する。 | 津田 吉晃 筑波大学山岳科学センター菅平高原実験所 | 2025.4.1~2026.3.31 |
| 62. 歴史が生み出す二次的自然のホットスポット:環境価値と保全効果の「見える化」 | 本課題では、かけがえのない代替不可能な歴史が生み出す、半自然草原の生物多様性ホットスポットと新たな環境価値、そしてそれらに対する保全手段を明らかにし、「見える化」することを目的とする。これによって二次的自然に対する環境施策に貢献する。 | 丑丸 敦史 神戸大学人間発達環境学研究科 | 2025.4.1~2026.3.31 |
| 63. 大陸から隔離されて長野に分布する絶滅危惧植物ツキヌキソウの保全遺伝学的研究 | 実験所内および菅平高原地域におけるツキヌキソウ自生集団について、自生地の状況や生育環境の光条件、光合成能力などの調査を行う。実験所外の集団については、 DNA 解析用サンプルの採取も行う。サンプルはお茶の水女子大学に持ち帰り、DNA 解析を行うことで集団遺伝構造や遺伝的多様性を明らかにする。最終的には、集団遺伝構造や遺伝的多様性の情報を元に、長野県におけるツキヌキソウ集団の保全計画の策定に貢献することを目的とする。 | 岩崎 貴也 お茶の水女子大学 | 2025.7.10~2025.7.11 |
| 64. 千曲川の生物多様性研究 | 環境DNA、生態調査により千曲川流域の生物多様性を評価する | 加藤 駿 東北大学大学院生命科学研究科 | 2025.7.22~2026.3.31 |
| 65. 菌類調査 | 菅平高原実験所内の菌類相調査に参画する | 升屋 勇人 森林総合研究所 | 2025.7.28~2025.7.29 |
| 66. Poronia 属の一種の分類・生態 | 群馬県高崎市新町で発見した Poronia 属の分類上の位置、生態を明らかにすること。 | 石田 大和 菌類談話会 | 2025.8.4~2025.8.6 |
| 67. 林冠タワー上での大気環境DNA観測による昆虫相および菌類相の把握 | 各地域の生物多様性の比較的簡易な評価方法として、環境DNAの採集とそのメタバーコーディング解析が近年急速に注目を集めている。この分野は、まず魚類などの水圏生物相を把握する手段として注目され、海水及び淡水から環境 DNA を収集・解析する技術が発展してきた。それに対して、直近では胞子・花粉・細胞断片などのバイオエアゾルからの大気環境 DNA 収集より陸圏生物相を把握することが試みられているが、大気環境 DNA の効率的な採集方法は確立されていない。本研究では複数のエアロゾルサンプラーを用いて森林の林冠上で採集を行い、昆虫相及び菌相の多様性把握に適した大気環境 DNA の収集方法を模索する。 | 松永 寛之 筑波大学山岳科学センター菅平高原実験所 | 2025.8.20~2026.3.31 |
| 68. 食用昆虫の探索および森林・水生昆虫資源の調査 | 水生昆虫や森林昆虫の食利用の可能性を調査する | 水野 壮 NPO法人食用昆虫科学研究会 | 2025.9.8~2025.9.10 |
| 69. 半自然草原生植物の被食防御様式 | 半自然草原生植物の被食防御、特に化学的防御において、葉内に集積している化学物質を解明する。 | 森 瑞希 東京農業大学地域創成科学科 | 2025.8.18~2025.8.20 |
| 70. ドングリをテーマにした自然番組制作 | ドングリをテーマに自然番組を制作している。カケスの貯食行動を撮影するとともに、菅平実験林のミズナラ調査を取材し、ドングリが勢力を拡大するうえで重要な役割を果たしているとされるカケスとの関係を紐解き、映像化する。 | 柴垣 文香 NHKエンタープライズ | 2025.8.25~2026.3.31 |
| 71. 日本における山岳ツーリズムの持続性 | 日本の山岳ツーリズムは、近い将来、グローバルな現象である地球温暖化という問題に直面することが予測される。また山岳ツーリズムの拠点となることが多い山村では継続的な高齢化・人口減少で地域社会の存続が危惧されている。そうした問題点を有する山岳ツーリズムについて、菅平高原を対象にフィールドワークを実施し、それをもとに山岳ツーリズム全体の持続性を検討する。 | 呉羽 正昭 筑波大学生命環境系 | 2025.8.1~2026.3.31 |
| 72. | 実験所構内の森林において、冬虫夏草の発生実態を記録するために単発の踏査を実施する。本調査では、構内の代表的な林内ルートを巡回し、出現した冬虫夏草を観察・写真撮影し、必要最小限の標本を採集する。記録項目は採集日、位置(GPS)、生育基質、宿主の推定、写真番号などとし、統計的解析は行わず記述的に整理する。安全管理(単独入林禁止、危険生物への注意、許認可遵守)を徹底し、調査後は標本を適切に保管する。 | 高瀬 佑樹 | 2025.9.4~2025.9.6 |
| 73. 蜂類に寄生する冬虫夏草の発生場所や宿主の種類について調査を行い、蜂類と冬虫夏草のホストレースを解明する | 実験所構内の森林において、冬虫夏草の発生実態を記録するために単発の踏査を実施する。本調査では、構内の代表的な林内ルートを巡回し、出現した冬虫夏草を観察・写真撮影し、必要最小限の標本を採集する。記録項目は採集日、位置(GPS)、生育基質、宿主の推定、写真番号などとし、統計的解析は行わず記述的に整理する。安全管理(単独入林禁止、危険生物への注意、許認可遵守)を徹底し、調査後は標本を適切に保管する。 | 高橋 純一 京都産業大学生命科学部 | 2025.9.4~2025.9.6 |
| 74. 菅平高原産さび菌類相の調査 | 菅平高原実験所菌類相調査の一環として、菅平高原のさび菌類の多様性について明らかにすること。また、菌類相調査参加者へのさび菌の観察手法、同定手法について指導を行う。 | 山岡 裕一 筑波大学生命環境系 | 2025.10.1~2026.3.31 |
| 75. 菅平高原産硬質菌類相の調査 | 菅平高原実験所菌類相調査の一環として、菅平高原の硬質菌類の多様性について明らかにすること。また、菌類相調査参加者への硬質菌の観察手法、同定手法について指導を行う。 | 服部 力 森林総合研究所 | 2025.10.1~2026.3.31 |
| 76. 菅平高原に生育する遺存分布植物についての保全遺伝学的研究 | 菅平高原に生育する遺存分布植物であるツキヌキソウ、カラフトイバラ、クロビイタヤなどについて野外調査を行うとともに葉サンプルを採集して DNA 解析を行い、北海道などの他地域との間の遺伝的関係性を明らかにすることを目的とする。 | 岩崎 貴也 お茶の水女子大学基幹研究院自然科学系 | 2025.9.19~2025.9.20 |