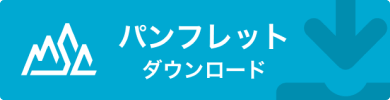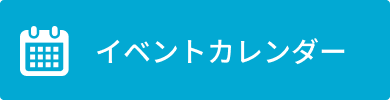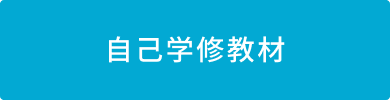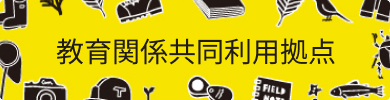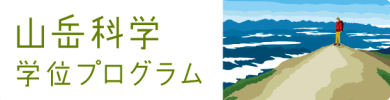菅平生き物通信
2009年より、菅平高原実験所ではフリーペーパー「菅平生き物通信」を発行しています(年5回、2024年2月現在)。生物に関する話題、菅平高原実験所で行われている研究の紹介、イベント情報などを掲載しています。紙媒体をご希望の方は、在庫を確認しますのでお問い合わせのうえ、菅平高原実験所までお越しください(平日のみ)。
バックナンバー
号数・発行年月・主な掲載内容
- 第110号(2025年12月)
田中健太さんを偲ぶ / 秋の道を通いながら - 第109号(2025年9月)
板目と柾目、木目と杢目で森を楽しむ / なぜ今、シカが問題になっているのか? - 第108号(2025年6月)
ムカシゴキブリ上科 ゴキブリ目の古の記憶? / 大学でのツキノワグマ研究 - 第107号(2025年4月)
総合技術研究会2025筑波大学 - 第106号(2025年2月)
芋虫や毛虫は蛾や蝶になる… / カエルの鳴き声を未来へ - 第105号(2024年12月)
菅平高原実験所構内全生物相の解明に向けて / 「味噌玉味噌」を知っていますか? - 第104号(2024年9月)
成熟草原って何? / 共生? 寄生? お前はどっち!? ~謎多き菌類ラブルベニア~ - 第103号(2024年6月)
野辺山高原の大学の森 / 樹木園 花と果実の暦 - 第102号(2024年4月)
自慢したい昆虫ばかりですがとにかく日本が誇りたい昆虫! / ナチュラリスト募集のお知らせ - 第101号(2024年2月)
ようこそ! 魅惑のゴキブリワールドへ / 糞生菌 ~フンから生えてもかわいい菌類~ - 第100号(2023年12月)
林一六先生への感謝 / 菅平生き物標本展が開催される - 第99号(2023年10月)
ボランティアと進める標本整理 - 第98号(2023年9月)
外来魚コクチバスとブルーギルの特殊な産卵行動 / 小さな楽園「変形菌」 - 第97号(2023年6月)
雪上に現れるふしぎな星 キオナスター「ユキボシ」の謎 / 木の身体測定 毎木調査 - 第96号(2023年4月)
採集×標本×史料 時をかける生物多様性研究 / ナチュラリスト募集のお知らせ - 第95号(2023年2月)
信州・菅平の気候とその変動 ~雪と私~ / クワガタムシの遺伝子汚染 - 第94号(2022年12月)
テン / イトエダカビ ~美しき寄生菌の不思議な生き様~ - 第93号(2022年10月)
シルクロードを渡ったリンゴ / 身近な白いチョウのいろいろ - 第92号(2022年9月)
美しい侵略者 オオキンケイギクの防除 ~長野県の貴重な自然を守る~ / 冬虫夏草の世界 ~虫から生える不思議なキノコの話~ - 第91号(2022年6月)
求む!「味噌玉」情報 ~絶滅危惧の伝統知、玉味噌仕込みを追って~ / クマと人間と豊かな森を繋ぐ連携プレー ~ピッキオでの経験を通して~ - 第90号(2022年4月)
日本列島固有科のガガンボカゲロウ ~地殻変動の生物への影響~ / ナチュラリスト募集のお知らせ - 第89号(2022年2月)
菅平高原の雪と微気象 / 菅平ナチュラリストの会 2021年の活動より / 私の菅平での楽しい生活 - 第88号(2021年12月)
タヌキ・キツネ・イヌの足痕・足跡くらべ / 春よ来い! ~春先に芽生えるウスバサイシン~ / 偏食家の中の変わり者 キアゲハ - 第87号(2021年10月)
4億年生きるカゲロウの魅力 / クワガタムシの武器 ~大顎~ - 第86号(2021年9月)
伝承からみる生物の歴史 ~言い伝えを後世に残すには?~ / もしもしかめよかめさんよ / 知られざる前胃の不思議 - 第85号(2021年6月)
古いものは良い ~草原の歴史が持つ価値~ / 初夏の訪れを告げるエゾハルゼミ / Metschnikowia メチニコビア属 - 第84号(2021年4月)
山岳微生物学の授業から ~山辺糀店さんの糀作り~ / 浜の宝探し ~深海魚拾い~ / 植物の名前 - 第83号(2021年2月)
キジとヤマドリ ~足痕は3本指~ / きのこに生えるカビ / 東京の空の下で想い続けた菅平の風景 - 第82号(2020年12月)
フウセンモのハリセンボン / スマートフォンで広がる生物分布調査 / 初めての信州生活 - 第81号(2020年11月)
「地衣類」でもあり「きのこ」でもある 担子地衣類の多様な世界 / 爬虫類は面白い! ~ヘビ編~ / ツキノワグマの存在 - 第80号(2020年9月)
コロナ禍における人間と野生動物との関係 ~ロックダウン効果~ / 台風に負けない! / 咲いてます、樹木 - 第79号(2020年6月)
新型コロナウイルスとの共生 / 生活を想像する楽しみ / スイス渡航記 - 第78号(2020年4月)
2019年度発酵食品講座を振り返って ~微生物たちとのよいつきあいを目指して~ / やっと出会えたミナミカワゲラ亜目 / カモシカとのつきあい方 - 第77号(2020年1月)
湿原に出かけよう / 刺さないハチ? ~針から読み解くハチの進化~ / コケに咲く花のようなチャワンタケ! - 第76号(2019年12月)
菌類に寄生する植物 /スキー場の花々 / 近くて遠いコウマクノウキン類 - 第75号(2019年10月)
微生物研究の原点にして頂点、純粋培養 / 日本の竹と竹を通して考えたこと / 地域社会の形成・発展のため連携協定締結(上田市と山岳科学センター) - 第74号(2019年9月)
私たちに身近な昆虫、「多新翅類」 ~その祖先の姿、系統関係がみえてきた!~ - 第73号(2019年7月)
イタリアの思い出 / 蛾 ~その意外な美しさ~ / 自然の息吹から感じた人命の尊さ - 第72号(2019年6月)
外来種のどこが問題なのか(1) / クサカゲロウと酵母の関係 / かけがえのない生態系…菅平湿原 - 第71号(2019年4月)
「社会のダニ」ならぬ「ダニの社会」PARTⅡ / 相模湾で増える南からの魚たち - 第70号(2019年2月)
害虫カメムシはヒーローか!? 夢のようなはなし / 生き物観察とスケッチ - 第69号(2019年1月)
菅平湿原の輝く水 / 書籍紹介「原色川虫図鑑 成虫編」 /冬の樹木園散歩 - 第68号(2018年12月)
いっぱいあったらお得なのか? / 身近になるドローン / きのこの上に生える黒い虫ピン ~ファエオカリキウム・ポリポラエウム~ - 第67号(2018年10月)
クマと危険遭遇しないように / 意外と知らない!? セミのお話 - 第66号(2018年8月)
イタリア ~地中海の森林植生~ / 目指せ、カビマスター! / 須坂市へのすゝめ - 第65号(2018年7月)
品種資源と種子法 / 磯の生き物を見に行こう! / 古き草原を知る - 第64号(2018年6月)
「社会のダニ」ならぬ「ダニの社会」 / マダラナギナタハバチ ~最も原始的な完全変態類~ / カモシカのような足? - 第63号(2018年4月)
雪解け後の枯草を「シミガレ」って呼んでますか? / 味噌作りの源流「味噌玉」 - 第62号(2018年2月)
生物と分布域 / 十人十色のナミテントウ / 紹介します!! ニホンノウサギ(Lepus brachyurus) - 第61号(2018年1月)
昆虫の翅はどこから出来たのか / 会えたら嬉しい赤い鳥 ~オオマシコ~ / 紹介します!! ニホンリス(Sciurus lis) / 冬芽観察 ~春を待つ木々たち~ - 第60号(2017年12月)
豪雪地へ移り住んだ高山植物:ミヤマキンバイにみる環境への適応 / 藻類といつも一緒のシラウオタケ / 冬にやってくる鳥 ーツグミー - 第59号(2017年11月)
外来種と遺伝的多様性 / 増えるニホンジカ / 紹介します!! クロウスタビガ / 意外と身近な「変形菌」 - 第58号(2017年9月)
ヒメシジミにみる生物の個性 ~個体変異~ / 酵母に寄せて 大学院生 山田宗樹君のこと / 土壌動物を見てみよう /キノコ・カビ・酵母 ー海藻サラダに隠された秘密!? - 第57号(2017年7月)
山の日と渓流釣り / 肉眼で見える1つの細胞 / 紹介します!! ニセツマアカシャチホコ - 第56号(2017年6月)
今年は雪が多かった!? / 縄文から続く(?)草原はスゴイ /水に住むカビの話 - 第55号(2017年4月)
シミ ~人とともに生きてきた昆虫~ / 書籍紹介「ざざ虫 ~伊那谷の虫を食べる文化~」 - 第54号(2017年2月)
子育てをする虫 モンシデムシ / 単細胞だって凄いんです! / ワラビをめぐる葛藤2 採るべきか採らざるべきか - 第53号(2017年1月)
新年のごあいさつ / 古くて新しいシダ植物 / 微生物 色々 / 自然をみる - 第52号(2016年12月)
小さな隣人たちⅤ ~花を訪れる酵母たち~ / アイスランドへ行ってきました / 身近にいる愛らしい生き物 ヤスデ - 第51号(2016年10月)
インドの山奥 都市化と伝統文化の狭間で / 糞生菌観察の魅力 / 少し変わった標本作り ~翅を開いてみよう~ - 第50号(2016年9月)
花を訪れる昆虫たち / ハジラミ ~翅がないのに大空を飛び回る昆虫~ / ムラサキシャチホコ / 植物図を知っていますか? - 第49号(2016年7月)
イシノミ ~原始の特徴を今につたえる昆虫~ / ユウスゲ / 紹介します!! エゾヨツメ / 小さな体で賢く生きるヒメシジミ - 第48号(2016年6月)
菅平高原実験センターのオオブタクサ / 紹介します!! イボタガ / 書籍紹介「奇妙な菌類 ミクロ世界の生存戦略」 - 第47号(2016年4月)
母は偉大! ー昆虫の産卵場所選択ー / 酵母の「我慢大会」と花の蜜 / センター内の桜 ~冬を越えて花咲く季節~ - 第46号(2016年2月)
減りゆく根子岳の草原 ー冬景色から見えることー / 菅平高原でまたまた新種発見!! / 雪の結晶のレプリカを作ってみよう! - 第45号(2016年1月)
命とは何か / カワゲラウォッチ 冬の陣 / 山椒魚を探しに行こう / 地下生菌 ~地下に潜ったきのこたち~ / 変形菌の子実体の上に現れる変わり者 変形菌生菌類 / 四季の七草 - 第44号(2015年12月)
生物集団の過去の歴史を探る ~温暖化影響評価のために~ / 紹介します!! 原生粘菌 / 夏の実習シーズン / ノミの心臓はどこにある? ー昆虫の心臓ー - 第43号(2015年10月)
ササいな存在、けど気になる生き物たち PARTⅢ / キノコ・カビ・酵母 ー海藻サラダに隠された秘密!? /かはげら草子 - 第42号(2015年9月)
ドングリとツキノワグマ / 植物を縁の下から支えるアーバスキュラー菌根 / 初秋を感じさせるマツムシソウ / 噛む口、吸う口、舐める口 ー昆虫類の多様な口器ー - 第41号(2015年7月)
小さな隣人たちⅣ ~共生とは?~ / 365日クワガタ採集 / サクラの葉についた虫こぶ - 第40号(2015年6月)
生き物に力を借りるエコ減災 / 菅平高原で新種発見!! 地中で暮らすタマキノコムシ科の一種 / 菅平高原で新種発見!! 新属新種のツボカビ Cyclopsomyces plurioperculatus / 紹介します!! オオフタオビドロバチ - 第39号(2015年2月)
植物の押し葉標本 / 刺すハチ、刺せないハチ / 紹介します!! キイチゴの仲間 / 菅平の積雪 ~観測記録から~ - 第38号(2015年1月)
やっと昆虫の進化が見えてきた! / 昆虫のお腹の中にも菌類 / 紹介します!! 細胞性粘菌 / 国際菌学会に参加してきました! - 第37号(2014年12月)
ササいな存在、けど気になる生き物たち PARTⅡ / 藻類に寄生するツボカビ / 色々なハチの巣 / 冬の虫 ~翅が退化したフユシャク~ - 第36号(2014年10月)
ササいな存在、けど気になる生き物たち PARTⅠ / 水中の生産者「藻類」 / 減少する秋の七草 / 紹介します!! アケビコノハ - 第35号(2014年9月)
菅平での温暖化と植生の変化 / カッコウのつば? / 不思議な甲虫 ナガヒラタムシ / アブラムシの繁殖戦略 - 第34号(2014年7月)
朝日の熱帯雨林 / やっぱり昆虫採集! / カビを釣りに行こう!? / 質問コーナー(女王蜂の生態について) - 第33号(2014年6月)
小さな隣人たちⅢ ~地衣類の戸籍簿作成調査~ / キレイだけど危険! 毒を持つ植物たち / 紹介します!! セキレイの仲間 月夜の熱帯雨林 - 第32号(2014年4月)
マツ材線虫病を巡る生物 / はるばる海からやってきたウミホタルたち / 紹介します!! 冬の鳥たち / 陸に進出した「サビフクロカビ」 - 第31号(2014年1月)
新年のごあいさつ / 冬の動物達 / 冬を乗り越える虫たち / 他虫の空似 / 風にそよぐポプラの葉 / コムシ目紹介ホームページができました! - 第30号(2013年12月)
小さな隣人たちⅡ ~実は役に立つ 身近な生きもの 地衣類 / 良く似た形の生き物 / 空飛ぶ毛玉 ーマルハナバチってどんなハチ? / 盤菌類 ~多種多様な茶碗たち~ - 第29号(2013年10月)
小さな隣人たちⅠ ~土蜘蛛と梅の木苔~ / 「きのこ」ってなに? / ツボカビと接合菌 / 秋の虫は、なぜ鳴くの? - 第28号(2013年9月)
植物同士もたまに助け合う / 虫からキノコが… / ハサミムシのハサミ ~多様な形とそのはたらき~ / 書籍紹介 シロアリってすごい - 第27号(2013年6月)
なぜ蛾は光に集まるの? / 脱皮とクチクラの不思議 / 書籍紹介 土の中に住む小さな生きものたちを美しい写真とともに紹介 / 粘菌観察してみませんか - 第26号(2013年4月)
菅平高原は何故寒い? / 行ってきました! フィラデルフィア② / 紹介します!! カブトガニ科カブトガニ属 カブトガニ / 書籍紹介 この卵を産んだのは誰…?? そんな疑問に答えてくれる本が出ました! - 第25号(2013年2月)
動的平衡な生態系 / 紹介します!! カワガラス科カワガラス属 カワガラス / ホロタイプ標本を見にロンドン自然史博物館へ! / 行ってきました! フィラデルフィア① - 第24号(2013年1月)
書籍紹介 アリの巣の中で繰り広げられる驚きの世界! / 紹介します!! シラカンバ / 巨大野生キノコの正体はエノキタケ!? / こんなもの見つけました! 動物編 / 身近な生き物 テン - 第23号(2012年12月)
生命をつなぐ動物達 / 甘酒はどうして甘いの? /樹木園の四季 秋・冬編 / 紹介します!! シロアリ - 第22号(2012年11月)
植物に生える小さな毛の話 ーその機能と意義ー / 紹介します!! 結婚するために目が飛び出ちゃった昆虫たち / 樹木園の四季 春・夏編 / どんな仕事? 技術職員 - 第21号(2012年10月)
土壌中に潜む種子を探る / オオブタクサはなぜ花粉をたくさん飛ばすのか? / 第24回国際昆虫学会議 in Korea / 紹介します!! キク科オオハンゴンソウ属 オオハンゴンソウ - 第20号(2012年9月)
なんで生き物を守るの?⑤ 畑から雑草が消えたあと / 草原観察から分かった新発見! / マレーシア旅行記② / 紹介します!! 絶滅危惧種とは? - 第19号(2012年7月)
高山植物と植物につく菌の関係について / マレーシア旅行記① / 紹介します!! 植物・昆虫・菌 / 水の安定同位体について その2 - 第18号(2012年6月)
草原の変化を見つめる④ ワラビをめぐる葛藤 / 水の安定同位体について その1 / 紹介します!! ゴキブリ★いろいろ / なんで生き物を守るの?④ 生き物からのグッド・アイデア - 第17号(2012年4月)
植物の生き方を形から考える / なんで生き物を守るの?③ たくさんの生き物が織りなす生態系の恵み / 水中を泳ぐカビ!?「ツボカビ」 / 紹介します!! ユリ科カタクリ属 カタクリ - 第16号(2012年2月)
本州一寒い場所 菅平高原 / 生態系に影響を与えるニホンジカ ー浅間山でも増加ー / 紹介します!! ヤドリギ科ヤドリギ属 ヤドリギ - 第15号(2012年1月)
明けましておめでとうございます / コブハサミムシ 生命のリレー / なんで生き物を守るの?② 35億年の歴史遺産から生まれる新薬 / 紹介します!! シカ科シカ属 ニホンジカ - 第14号(2011年12月)
粘菌はともだち? / ~ブナ林と共に生きるカミキリムシ~ ヨコヤマヒゲナガカミキリ / 第9回環境研究シンポジウム参加報告 / 紹介します!! マツ科トウヒ属 ドイツトウヒ - 第13号(2011年11月)
生き物の歴史と放射線 / なんで生き物を守るの?① 在来品種の力 ~緑の革命~ / 草原の変化を見つめる(3)ーワラビを採ると草原はどうなるかー - 第12号(2011年10月)
氷河期が残した北の植物 / 毒キノコトリオをご紹介します / フェアリーリング(菌輪) / アオダイショウ(青大将) - 第11号(2011年9月)
菅平実験センターつれづれ / 昆虫は口で呼吸をしない! 巨大キリギリスの大きな気門 / 温暖化実験 ~西駒演習林にて~ - 第10号(2011年7月)
夏休み研究紹介 / Mouthparts of Grasshopper / 春の自然観察会報告 - 第9号(2011年6月)
昆虫は脚で食べている! / コムシが誘う自然への入口 / 夢のマレーシア - 第8号(2011年4月)
高原の息吹を皆様に / 林内にセンサーカメラ設置 - 第7号(2011年3月)
木を伐るのは悪いこと? 最終回 ー自由貿易に翻弄される自然ー / アケビコノハ / ナチュラリスト養成講座 成果発表会 修了式 - 第6号(2010年12月)
大明神宿舎の建築的価値 / ナチュラリスト養成講座受講生による大明神宿舎の柿渋塗り作業 / 地球の生き物を守り、その恵みを公平に分けるしくみ作り ーCOP10参加レポートー - 第5号(2010年9月)
- 第4号(2010年6月)
- 第3号(2010年3月)
- 第2号(2009年11月)
- 創刊号(2009年8月)